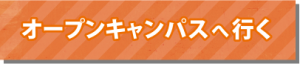保育士コラム

小規模保育園とは?特徴や働くメリット・デメリットについて解説

小規模保育園とは待機児童問題の解消を目的に設置された保育施設のことです。小規模保育園の施設数は増加傾向ですが、一般的な保育園と具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
本記事では、保育士を目指す人に向けて小規模保育園が増えている理由や、小規模保育園で働くメリット・デメリットなどを紹介します。小規模保育園の特徴を理解し、自分にあった職場を選びましょう。
目次
非表示
小規模保育園とは
小規模保育園の種類は一つではなく、大きく3つに分けられます。まずは、小規模保育園の特徴や種類を一般的な保育園の違いと比較しながら解説します。
小規模保育園の特徴
もともと認可外だった小規模保育園は、2015年に「子ども・子育て支援新制度」が施行されたことにより市町村の認可事業となりました。
小規模保育園と一般的な保育園の大きな違いは、施設を利用できる子どもの年齢と定員数です。小規模保育園を利用できる子どもの対象年齢は0〜2歳児、定員数は6〜19人以下となっています。
一方、一般的な保育園は0〜5歳児までが対象で、定員数は20人以上となっています。そのため、これまで定員に達せず認可外だった保育園も、小規模保育園として認可を受けることが可能になりました。
小規模保育園の種類
小規模保育園は、A型・B型・C型の3つに大きく分けられます。分類の主なポイントは、定員・職員の資格・職員数・施設面積です。
A型の定員は6人以上19人以下で、すべての職員が保育士資格を取得していなければなりません。また、0〜1歳児は乳児室として1人あたり1.65㎡、ほふく室として3.3㎡、2歳児は保育室等として1.98㎡の施設面積が必要です。必要な職員数は一般的な保育所の配置基準に1人の追加配置となります。したがって、一般的な保育園の配置基準(0〜1歳児には園児3人につき職員1人、2歳児は園児6人に対して職員1人)にそれぞれ職員1人の追加配置となります。
B型は、職員全体の半数に保育士資格が必要です。また、定員・職員数・施設の面積はA型と同様です。
C型は、家庭的保育者のみで運営できる点が特徴です。家庭的保育者とは、自治体の研修を修了し保育士資格と同等の知識やスキルを有すると認められた人を指します。また、定員数は6〜10人、必要な職員数は0〜2歳児園児3人に対して1人です。なお、補助者を置く場合は園児5人に対して2人の職員が必要となります。また、必要な施設面積は、子どもの年齢を問わず園児1人あたり3.3㎡です。
※出典:厚生労働省.「関係事業等の概要について」(参照 2022-02-24)
小規模保育園が増える理由
小規模保育園誕生の背景には、待機児童問題の深刻化がうかがえます。待機児童の中でも、0~2歳児は特に受け入れが厳しい状況です。一般的な認可保育園に預けられずに職場復帰できない保護者もいれば、高額な費用を支払って認可外の保育園に預ける保護者もいます。
小規模保育園を増やす目的は、0〜2歳における待機児童数の低減です。小規模保育園は、一般的な認可保育園よりも施設面積が少なくて済みます。そのため、土地の確保が難しい都市部でも小規模保育園なら開園が可能です。
室内や園庭など広範囲を整備する手間がかからないため、小規模保育園なら短期間で開園できます。待機児童問題を解決する有効な手立てがない中、今後も小規模保育園は増え続けると予想されます。
小規模保育園で働くメリット

小規模保育園で働くと、一般的な保育園とは異なるメリットが得られます。ここでは、小規模保育園で働くメリットを解説します。
体力的に負担が少ない
小規模保育園が預かる子どもの対象年齢は、0〜2歳児です。0〜2歳児の運動量は3歳児と比べると少ないため、職員は体力を温存できます。また、定員が少ないため、業務連絡の書類や保護者に渡す資料などをスピーディーに作成でき、残業や持ち帰りの仕事を減らせます。
行事による負担が少ない
0〜2歳児を預かる小規模保育では、運動会や発表会のような大規模な行事が少ない傾向です。また行事があっても、少人数であれば準備にそれほど負担がかかりません。行事に時間を割かない分、職員は普段の保育に注力できるでしょう。
職員や保護者と連携しやすい
子どもの人数が少ない小規模保育園では、一般的な保育園よりも子どもと保護者の顔を覚えやすい傾向です。また、職員数も少ないため全員で連携しやすく、保育園全体で保育に取り組んでいる実感をもてます。
子どもや保護者と熱心に向き合いたいと考える人にとって、小規模保育園の環境はおすすめです。
小規模保育園で働くデメリット

小規模保育園で働く際は、職員の資格や人数、施設の面積を確認しておくことも大切です。小規模保育園で働く際に、デメリットと考えられることを解説します。
保育士のスキルに差がある
B型やC型の保育園は、保育士資格を持っていなくても働けます。職員のスキルに差があれば、安全面などで保育士資格保有者の負担が大きくなるケースがあります。
また保育士資格がある人でも、3歳以上の保育経験しかなければ適切な対応ができないかもしれません。スキル不足を補うために小規模保育園では職員同士の協力が必須です。
保育士の人数が少ない
子どもの人数が少ない小規模保育園では職員の人数も少なめです。職員に欠員が出ると他の職員でカバーしなければなりません。ギリギリの人数で対応している園では休みを取りにくい場合があります。
保育スペースが狭い
省スペースで開園できる点は小規模保育園の魅力です。しかし、実際に働く職員からすると保育スペースの狭さはデメリットにもなり得るでしょう。
狭い空間で子どもを遊ばせるためには職員の工夫が必要です。特に園庭がない保育園では外遊びのたびに子どもたちを外に連れ出す必要があります。
小規模保育園の特徴を理解して自分に合った保育園を選ぼう
0〜2歳児を対象とする小規模保育園で働く場合、職員は体力の負担や行事の手間を抑えられます。また、他の職員や保護者と密に連携できる点も小規模保育園のメリットです。
一方、小規模保育園では職員のスキルにバラつきがあるケースも少なくありません。職員の人数や施設面積なども確認して、働きやすい小規模保育園を選びましょう。
日本児童教育専門学校 講師
保育のお仕事コラム 他
保育のお仕事コラム 編集チームでは、保育士の方、保育士を目指している学生、社会人の方に、保育士のなり方や働き方、保育に関する情報を発信していきます。
保育士・幼稚園教諭免許の資格取得なら東京都新宿区高田馬場にある保育士専門学校の「日本児童教育専門学校」へお問い合わせください