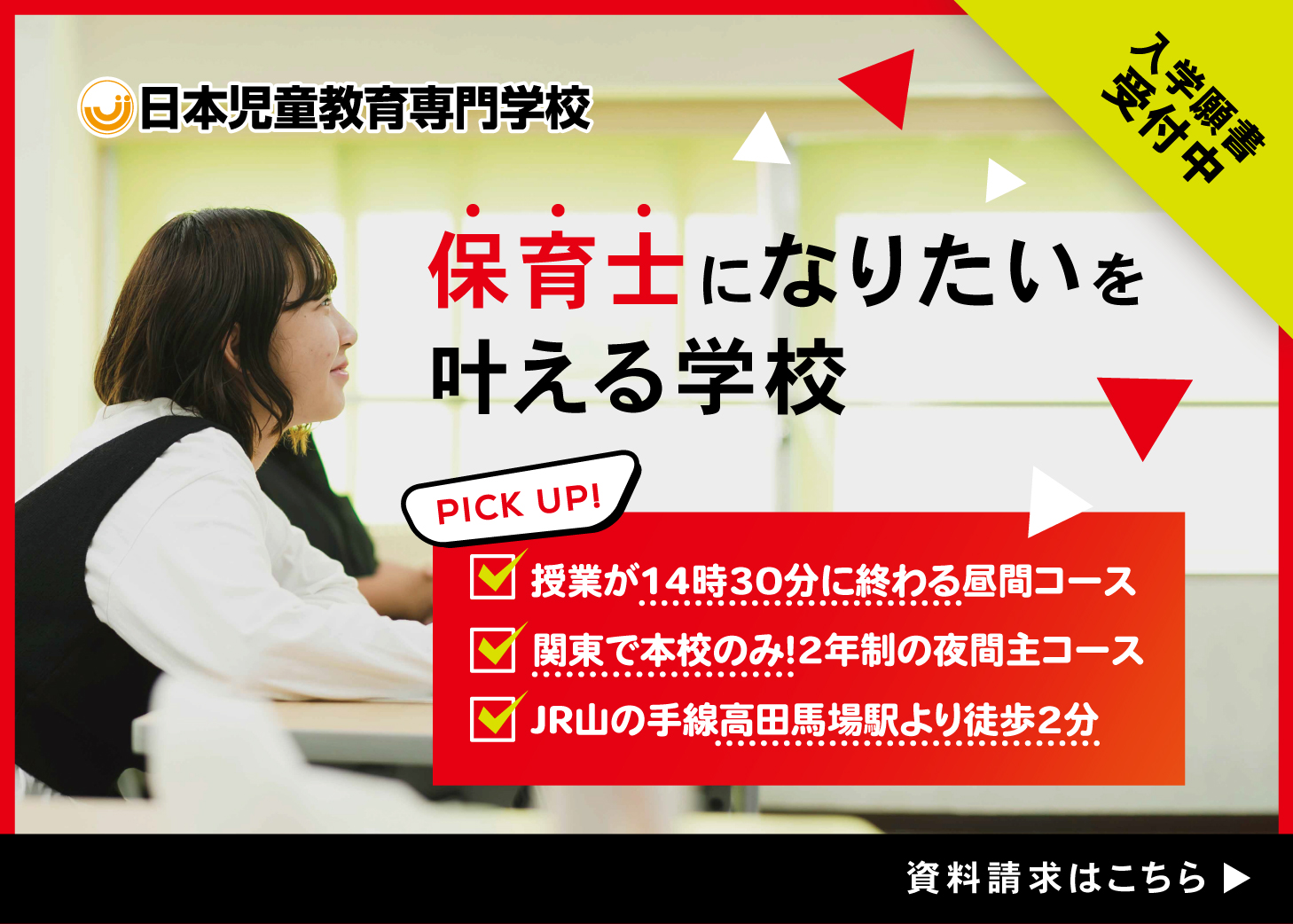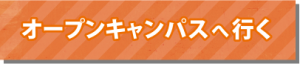保育士コラム

保育士でも医療従事者になれる!病棟保育士と院内保育士の違いを解説

保育士は保育園でしか働けないというイメージがありますが、最近は病棟保育士や医療保育士として病院で働く人も増えています。
今回は、保育士の新たな働き方として注目されている病棟保育士と医療保育士に関する基礎知識や、医療保育専門士の資格についてまとめました。
目次
非表示
入院中の子供の心身をケアするのが仕事!病棟保育士・医療保育士の基礎知識
病棟保育士および医療保育士とは、病院内で子供のお世話やケアを行う保育士のことです。病院に入院している0歳~18歳までの子供を対象に、食事のお世話や着替えの手伝いといった日常生活の介助を行ったり、一緒に遊んで心のケアを図ったりするのが主な仕事です。
親元から離れて入院生活を送っている子どもたちは体だけでなく、心も不安定になりがちです。医師や看護師は、自分の仕事で忙しいのでなかなか子どもたちの相手をできませんが、病棟保育士や医療保育士なら子どもたちのお世話やケアに専念し、退院までの生活を全力でサポートすることが可能です。
健康な子供を対象とする一般的な保育園とは異なり、病気やケガで入院している子供を保育するため、医師や看護師と連携を取りながら業務に当たります。
病棟保育士と医療保育士の業務はほとんど同じ
病棟保育士と医療保育士は名前こそ異なりますが、院内で行う業務はほぼ共通しています。
そのため、病棟保育士と医療保育士は同じものと考えて差し支えありませんが、病院によっては医療保育士の方が看護面をサポートする役割が大きい場合もあります。
院内保育や病児保育・病後保育とは似て非なるもの
病棟保育士や医療保育士は「病院で働く保育士」ということで、よく「院内保育士」と混同されがちです。
しかし、病棟保育士や医療保育士が入院中の子供のケアを担当しているのに対し、院内保育士は医療機関職員の子供を預かる院内託児施設のスタッフとして働いています。
職場や担当する子供が根本的に異なるので、混同しないよう注意しましょう。一方の「病児保育士」や「病後保育士」は、親が連れてきた病気あるいは病後間もない子供を医療機関や子供の自宅で看るのが仕事です。
一時預かりのようなものですので、やはり入院中の子供のお世話やケアを担当する病棟保育士や医療保育士とは異なります。
病棟保育士と医療保育士のやりがいって?
入院中の子どもたちのお世話やケアを担当する病棟保育士や医療保育士、やりがいってどのような点でしょうか?
親元を離れて・・・それだけでも不安な中、辛い治療を頑張らなければいけない入院中の子どもたち。
そんな子どもたちの「心のよりどころ、安全基地」のような存在が病棟保育士、医療保育士です。
入院生活の中で、医師や看護師はどうしても「注射や様々な処置をする」=痛いこと、いやなことをする、子どもたちにとって「こわい」「いやな」存在です。
しかし、病棟保育士や医療保育士は、病棟の中にいるけれど「痛いことをしない」「一緒に遊んだり、勉強をしたりしてくれる」=「優しい」「大好き」な存在です。
入院中の子どもたちにとって病棟保育士や医療保育士は、辛い、痛い治療に一緒に立ち向かってくれる「味方」「同士」なのです。
病棟の中で病棟保育士、医療保育士は子どもたちから大人気です。病棟のあちらこちらから「保育士さ~ん!」と声がかかります。
このように、治療を頑張る子どもたちの病棟内での一番の応援団となり、子どもたちが辛い治療に立ち向かい、一日も早く退院できる!を心身ともに支える・・・これこそが病棟保育士、医療保育士の「やりがい」なのです。
保育士の資格があれば採用可能!病棟保育士・医療保育士になる方法
医療機関で働いているといっても、病棟保育士や医療保育士自身が医療行為を行うわけではありませんので、医師や看護師の資格は必要ありません。原則として保育士の資格を持っていれば誰でも病棟保育士・医療保育士として働けます。
ただ、お世話する子供は病気やケガで入院している子どもたちですし、意思や看護師とコミュニケーションを取ったり、カンファレンスに参加したりすることもありますので、医療や看護の知識は持っておくに越したことはないでしょう。
現場でより輝くために!患者と家族のQOL向上を目指す医療保育専門士
病棟保育士や医療保育士のニーズが上昇しているのを受け、日本医療保育学会が2007年より「医療保育専門士」の資格認定制度を開始しました。
専門的な保育を通じて、子供本人とその家族のQOL(生活の質)を向上させることを目的に制定されたもので、一定の資格を有したうえで資格認定研修会に参加し、所定の項目をクリアすれば認定証が交付されます。
認定研修を受講するための条件は3つある
医療保育専門士の認定研修を受講するには、3つの資格を有している必要があります。[注1]
- ・日本国の保育士資格を有していること
- ・病院、診療所、病児(後)保育室、障害児支援施設および乳児院(病・虚弱児介護加算対象施設に限る)などで、1年以上常勤するか、年間150日以上かつ2年以上の保育経験を有していること。
- ・日本医療保育学会の正会員であり、1年以上の会員歴があること。
これらすべての要件を満たした人は、資格認定のための参加登録を行うことで、認定研修を受けられます。
[注1]一般社団法人日本医療保育学会認定「医療保育専門士」資格認定実施要綱
http://www.iryouhoiku.jp/docs/pdf/2019jissi.pdf
医療保育専門士の資格認定までの流れ
医療保育専門士の資格認定研修に参加した後は、課題として研修レポートや事例研究論文を提出する必要があります。
その後、面接で口頭試問が行われ、晴れて合格すれば登録および認定手続きを経て医療保育専門士の認定証と認定カードを交付してもらえます。
病棟保育士・医療保育士の1日の流れ例
8:30
朝礼、看護師に子どもたちの状態、留意事項、本日の処置予定などを確認する。
9:00から10:00
各病室を巡回、必要に応じて授乳や清潔のケアを行う。
10:00から11:00
保育室(プレイルーム)に出てこられる子どもたちへ、それぞれの状態、発達に合った保育を提供する。
11:00から12:00
保育室(プレイルーム)で昼食介助、病室から出てこられない子どもたちへはベッドサイドで介助を行う。
12:00から13:00
休憩
13:00から15:00
病棟内は安静時間。各病室を巡回し個々に絵本を読み聞かせたり、不安な子どもたちの話しを聞いたり、安静の援助を実施。またこの時間に保育室(プレイルーム)の装飾などの保育準備も行う。
15:00
おやつ介助
16:00から17:00
医師や看護師、その他医療スタッフとの情報交換
17:00
退勤
まとめ
病棟保育士や医療保育士は心身に不調や不安を抱えている療養中の子供に対し、日常的な解除やメンタルケアを行うことを目的としています。
体も心も万全な状態で退院すれば、子どもたちの日常生活への復帰もスムーズになるでしょう。
あわせて医療保育専門士の資格も取得すれば、医療や看護の知識も身につき、現場でより活躍できるでしょう。
日本児童教育専門学校 講師
保育のお仕事コラム 他
保育のお仕事コラム 編集チームでは、保育士の方、保育士を目指している学生、社会人の方に、保育士のなり方や働き方、保育に関する情報を発信していきます。
保育士・幼稚園教諭免許の資格取得なら東京都新宿区高田馬場にある保育士専門学校の「日本児童教育専門学校」へお問い合わせください