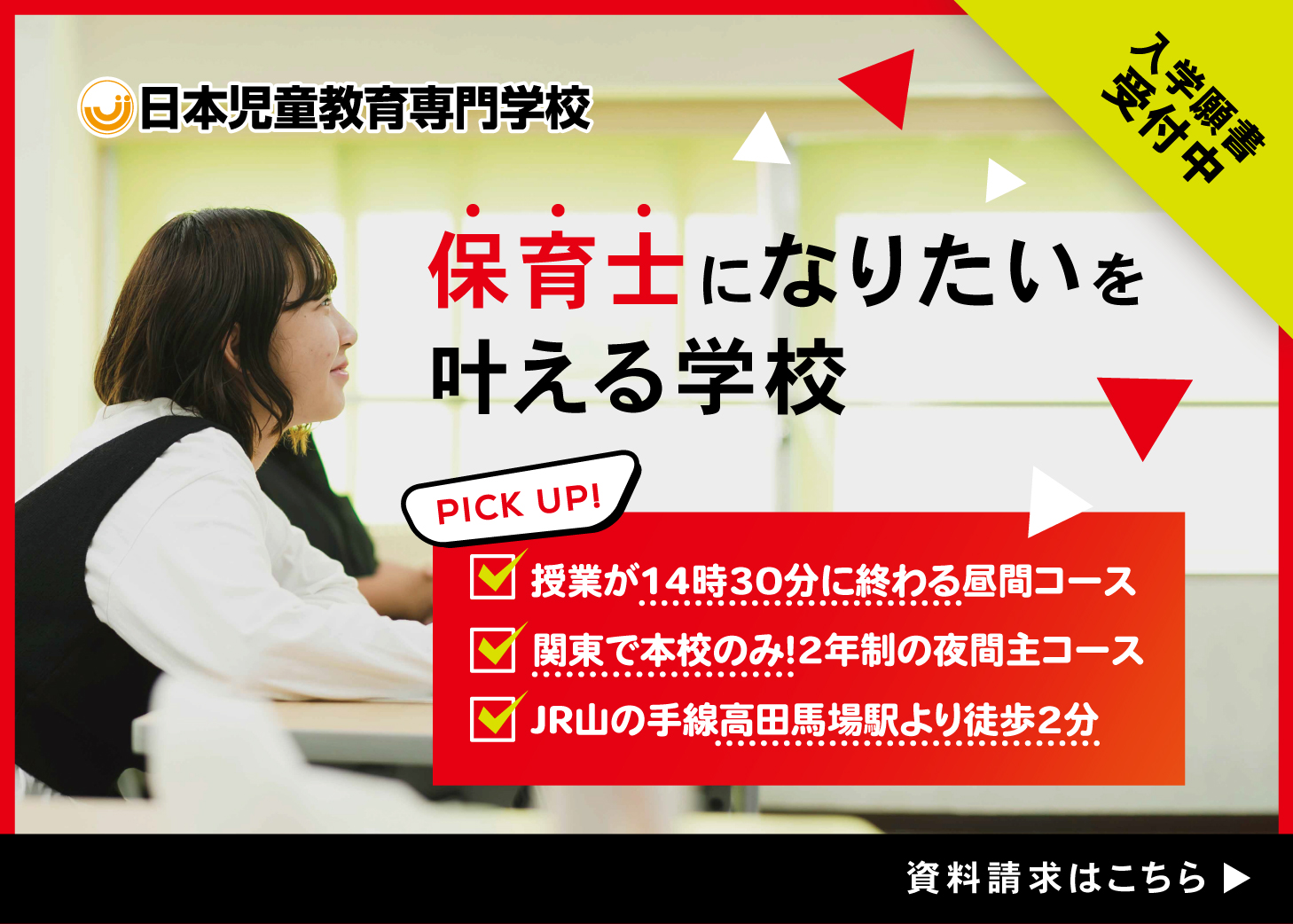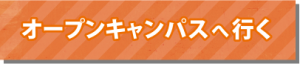保育士コラム

保育実習の際に押さえておきたいポイント!そもそも実習って何をするの?

保育実習は、保育士資格を取得するために必須のカリキュラムです。保育所、またはそのほかの児童福祉施設に趣いて実際の現場で保育士の仕事を体験、観察します。
保育実習はどんなものなのか、また保育実習ではどんな点に気をつけるべきなのかについてご紹介いたします。
目次
非表示
保育実習から学ぶ4つのこと
保育実習は、主に4つの種類があります。
それぞれに学べるポイントが違うので、事前にしっかり理解してから挑む必要があります。
子ども・保育者の様子を観察する「観察実習」
観察実習は、子どもや保育者がどんな行動をするのか、どんな対応が適切なのかを観察して記録する実習です。子ども個人の行動、子ども同士の関係、さらに保育者の対応などを観察していきます。
さらにその観察した内容と合わせて子どもや保育士の行動の意図や気づいた点を記録することで、次回からの自分の実習に役立てます。
保育士の補助を行う「参加実習」
実際の保育の場で、保育者の補助を行うのが参加実習です。
担当保育者の指導のもと、行動します。補助の立場ではありますが、子どもと実際に触れ合う機会も多く、子どもたちにとっては同じ「先生」です。
保育後には、観察実習の内容に加えて自分(実習生)の行動、その時の子どもの反応を記録します。それをもとに担当保育者と振り返りを行い、対応方法を身に着けていきます。
一つの場面の保育を行う「部分実習」
部分実習、または部分保育とも呼ばれます。
この部分実習では、絵本の読み聞かせや、手遊び、歌の練習などの一つの場面を保育者に変わり、実習生が保育を行います。
指導案を作成して、それをもとに保育を行い、保育後には記録し、振り返ることで子どもへの関わりで注意すべき点などを学ぶことができます。1回の実習で複数回行うこともある為、手遊びやエプロンシアター、ペープサートなどレパートリーが多いと安心です。また、保育士になったときにも役立つので、学生のうちにレパートリーを増やしておくと良いでしょう。
この部分実習では、自身が行った活動に対して、実際に子どもがどのようなリアクションをするのか観察できます。また、保育の中で、注意すべき点などを学ぶことができるため、「責任実習」で活かすことができます。
1日の保育を行う「責任実習」
責任実習では1日の保育をすべて任されます。
部分実習で学んだことを活かし、指導案はを作成し、保育を行います。遊びや一斉活動を行うだけでなく、子どもの健康状態のチェックや排泄の誘導、食事やお昼寝などの配慮も必要となるため、生活全般の知識が必要です。
一日を通して、保育士としての仕事を行い、振り返ることで、部分実習より更に多くのことを学ぶことができます。
また、実際に保育を行うことで、自分の苦手なことや強みを知ることができるため、保育士になるまでに、苦手を克服する、強みを増やすことができます。
保育実習で押さえておきたい3つのポイント
保育実習ではさまざまなことを学べますが、事前に押さえておきたいポイントがあります。
実習先がそのまま就職先になるケースも少なくありませんので、失礼のないよう、また何も学ばずに帰ってきてしまったということがないように注意していきましょう。
基本的なビジネスマナーを守る
実習と言っても実際の職場にお邪魔して体験をさせてもらいます。
遅刻や無断欠勤をしない、正しい言葉遣いをするなどの最低限のマナーはかならず守るようにしましょう。
とくに言葉遣いは、実習先の先生に失礼になるだけでなく子どもが真似をすることもあります。
挨拶、お礼、謝罪など、きちんと丁寧な言葉遣いを心がける必要があります。
服装・持ち物は事前に準備する
動きやすい服装、エプロン、名札など、実習先の保育所の指示に従いましょう。
髪の毛、爪、アクセサリーなども厳しく指定されている場合もあります。
実習日誌、指導案のほか、持ち物も忘れ物がないように事前に揃えておくましょう。
子どもたちを傷つけない配慮をする
また実習生の身であっても、子どもたちから見れば実習生も「先生」の1人です。配慮のない言動で子どもを傷つけないように注意深く接するようにしましょう。
子どもの名前や行動、交流関係をできるだけ覚えて、楽しく安全な時間を過ごせるようにしてあげることが大切です。
また、保育実習での体験は秘密保持を厳守しなければなりません。子どもの様子などを写真に撮影したり、SNSに書き込むなどの行為は絶対にしないようにしましょう。
まとめ
保育実習には、部分実習、責任実習、観察実習、さらに参加実習という種類があります。
それぞれで何を学ぶことになるのか、どんな準備が必要なのかをしっかり把握して当日に備えるようにしましょう。
保育実習は遊びやアルバイトではありません。
正しい言動を心がけ、実習先にも子どもや保護者にも迷惑がかからないよう、1人の保育者としての責任を持って挑むことが大切です。
日本児童教育専門学校 講師
保育の学校 他
保育の学校コラム 編集チームでは、保育士の方、保育士を目指している学生、社会人の方に、保育士のなり方や働き方、保育に関する情報を発信していきます。
保育士・幼稚園教諭免許の資格取得なら東京都新宿区高田馬場にある保育士専門学校の「日本児童教育専門学校」へお問い合わせください