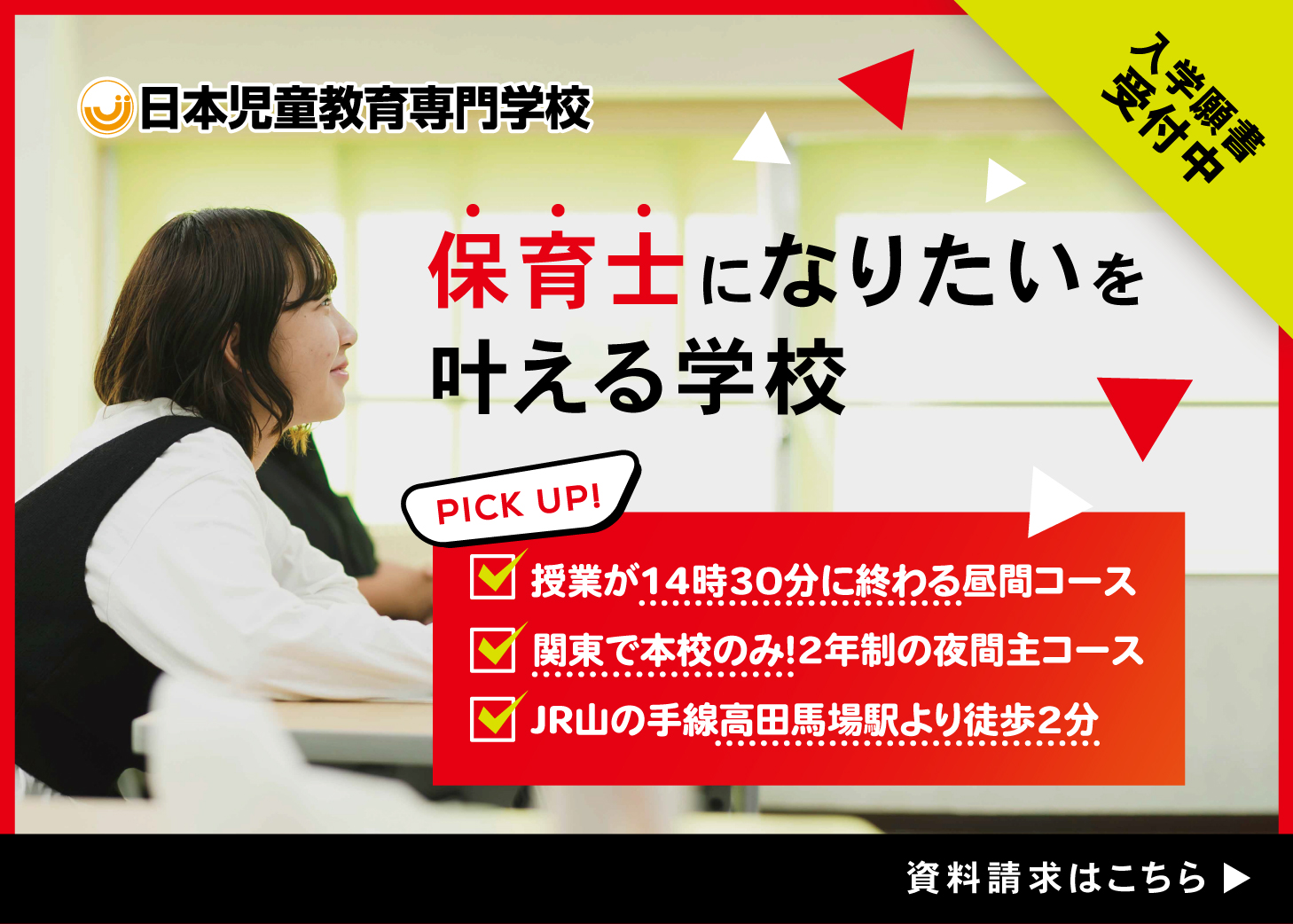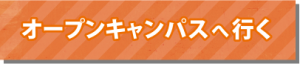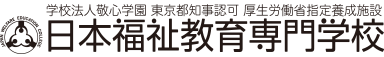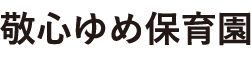保育士コラム
児童福祉司になるには?仕事内容や必要な資格を解説
公開日:2022年2月08日 更新日:2024年3月15日

児童福祉司は子どもや保護者の相談に乗りながら、問題解決のサポートを行う職種です。専門的な資格はなく、任用資格を満たすことで就職できます。
本記事では児童福祉司の仕事内容や、児童福祉司になるために必要なことなどを解説します。また児童指導員との違いもわかりやすく解説するので、これから児童福祉司を目指す方や2つの職種の違いを知りたい方はぜひ参考にしてください。
目次
非表示
児童福祉司とは?

児童福祉司とは、児童相談所に所属し、子どもや保護者の相談に乗りながら問題解決のサポートを行う職種です。児童相談所は平成28年時点で全国に209カ所あり、平成27年時点で児童福祉司の人口は2,900人ほどです。
各都道府県で児童福祉司の数が定められており、各児童相談所の管轄地域の人口4万人に1人以上を配置することが基本とされています。全国平均よりも虐待対応発生率が高い地域では、業務量に合わせて配置人数の上乗せを行うことになっています。
※児童虐待防止対策について. 「児童福祉司の概要等について」. (参照 2021-12-24).
児童指導員との違い
児童福祉司と似たような職種に、児童指導員があります。児童指導員は、指導福祉施設で生活を送る児童の保護者代わりとなって健全に成長できるようサポートする職種です。児童養護施設や福祉型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、児童家庭支援センターなどの職場に配属されます。
児童福祉司の職場は児童相談所に限定されますが、児童指導員は幅広い児童福祉施設へ配属されます。
児童指導員になるには児童指導員任用資格が必要で、誰でもすぐになれるわけではありません。この点は児童福祉司と同様です。
児童福祉司の仕事内容
児童福祉司の主な仕事内容は以下のとおりです。
・子どもや保護者から子どもの福祉に関する相談に応じる
・子ども・保護者の置かれている環境などを調査する
・子ども・保護者・関係者に必要な支援・指導を行う
・子ども・保護者の関係調整を行う
この他、講演会や講習会の開催、巡回相談なども児童福祉司の仕事に含まれます。子どもや保護者からの信頼がとても重要な仕事です。相手の話にしっかり耳を傾け、相手の立場に立って考えられる人が適しているでしょう。
子どもや保護者の相談を聞いて、的確に事情を把握できることが大切です。
児童福祉司に資格は必要ない
児童福祉司になるために資格は必要ありません。代わりに任用資格を取得している必要があります。児童福祉司任用資格を取得する条件は次のとおりです。いずれか一つでも該当していれば、任用資格を取得できます。
・都道府県知事の指定する児童福祉司等養成校を卒業
・都道府県知事の指定する講習会の課程を修了
・大学で心理学または社会学を専修する学科を卒業し、指定施設で1年以上相談援助業務に従事
・社会福祉主事として2年以上に従事した後、特定の講習を修了
この他、医師や社会福祉士なども児童福祉司任用資格を取得できます。
児童福祉司になる方法は?

児童福祉司になる方法はいくつかありますが、ここでは具体的な方法を解説します。
児童福祉司の専門学校を卒業する
児童福祉司の任用資格を取得できる専門学校を卒業する方法です。都道府県知事の指定する専門学校での卒業が必要となり、以下の専門学校が指定されています。
・国立武蔵野学院付属児童自立支援専門員養成所
・国立障害者リハビリテーションセンター学院児童指導員科
・上智社会福祉専門学校 社会福祉士・児童指導員科
国立武蔵野学院付属児童自立支援専門員養成所は埼玉県さいたま市にある養成所で、国が運営しているため授業料や寮費は無料です。待遇が良い分受験資格が一般的な専門学校と比べるとやや厳しめなのが特徴です。一般選考・公務員選考合わせて40名の採用枠です。
国立障害者リハビリテーションセンター学院児童指導員科は埼玉県所沢市にある国立の教育機関です。募集条件に年齢の制限がないのが大きな特徴です。ただし4年制大学を卒業しているか、保育士資格を取得していなくてはいけません。
上智社会福祉専門学校 社会福祉士・児童指導員科は東京都千代田区にある専門学校です。上記2つの学校と比べて出願資格が緩く、夜間過程のため仕事をしながら卒業できます。
専門学校なら児童福祉司に必要な知識を深く学べます。
都道府県知事の指定する講習会課程を修了する
都道府県知事の指定する講習会課程を修了することでも、児童福祉司になれます。講習会は1週間程度に渡って行われ、厚生労働省の示す基準に基づき研修内容が定められています。
現在指定されている講習会は『社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉学院 児童福祉司資格認定通信課程』です。約1年間、通信課程の受講で修了できます。専門学校と比べ安価で修了できるのが特徴です。
児童発達支援事業所や放課後デイサービス等児童福祉に関わる業務に携わる職員が対象のため、現在他の仕事に就いている場合はこの講習会課程に申し込めません。まずは受講資格をクリアする必要があるでしょう。
大学・大学院で指定の科目を履修し、施設で1年以上相談援助業務に従事する
専門学校や講習会でなくても、大学や大学院で指定科目を履修し、施設で1年以上相談援助業務に従事していれば児童福祉司になることができます。
厚生労働省に指定されている科目は、心理学・教育学・社会学です。これらを専修する学科のある大学・大学院に入学するとよいでしょう。
特定の職業で働き、1~2年以上相談援助業務に従事した後、指定の講習を修了する
特定の職業で働き1~2年以上相談援助業務に従事後、厚生労働大臣の定める児童福祉司任用前講習会等の講習会過程を修了し児童福祉司になる方法もあります。
特定の職業とは、社会福祉主事や助産師・教員(1種)・保健師・助産師・保育士・教員(2種)・児童指導員などです。職業によって、相談援助業務従事の指定期間が異なります。
※児童虐待防止対策について. 「児童福祉司の概要等について」. (参照 2021-12-24).
児童福祉司にふさわしい人
児童相談所はこどもとその保護者が相談に来ます。主な相談内容は次の通り、家庭によってさまざまです。
① 養護相談・・・保護者の家出、失踪、死亡、入院等による養育困難、虐待、養子縁組等に関する相談
② 保健相談・・・未熟児、疾患等に関する相談
③ 障害相談・・・肢体不自由、視聴覚・言語発達・重症心身・知的障害、自閉症等に関する相談
④ 非行相談・・・ぐ犯行為、触法行為、問題行動のある子どもに等に関する相談
⑤ 育成相談・・・家庭内のしつけ、不登校、進学適性等に関する相談
⑥ その他
児童福祉司は子どもとその保護者からこれらの話を聞き、多くの専門職と連携して支援をしていきます。
児童福祉司を目指そうと考えている方々はもちろん「子どもが好き」だと思いますが、児童福祉司の仕事は子どもだけでなく保護者や関係機関などの大人と接する仕事であることがお分かりいただけるでしょうか。
そのため児童福祉司になる人には「コミュニケーション力」が欠かせません。悩みを抱える子どもと保護者の気持ちに想いを馳せ、問題の全体像が掴めるようにお話を伺う必要があります。
また、これらの問題はチームで対応していきます。児童相談所内の職員をはじめ、子どもが通う学校や病院の職員と連絡を取り合ったり、会議を行ったりする機会も多々あります。「協調性」がなければ務まらない仕事なのです。そのとき、子どもや保護者のプライバシーを守るために個人情報の取り扱いには十分気をつけなければなりません。そのような「倫理観」も身につけていることが大事です。
さらに、子どもや保護者のお話を伺うときに必要となる力に焦点を当ててみましょう。
児童相談所に訪れる方々は多くの場合、不安、悲しみ、緊張といった気持ちを抱いています。相談することで解決できるのだろうか?という疑念もあるかもしれません。そのような不安感や疑念を和らげ、「児童福祉司の○○さんになら自分の話をしても大丈夫だ」「相談することが自分のためになる」と信頼してもらえるようにお話を伺う姿勢が大事です。そのためには相談者の話を傾聴し、悩みや困り感に共感するような技術が必要になります。これらの姿勢は「カウンセリングマインド」と呼ばれますが、そのような心理学・カウンセリングの知識を身につけていたり、興味がある方は児童福祉司に向いていると言えるでしょう。
また、児童福祉司は問題解決のためにこどもや保護者に助言をする場面も多くあります。そのとき心理学だけでなく社会学などの知識があると役立ちます。
幅広い分野に興味を持って学ぶことが児童福祉司の糧となります。
※相談内容について.「児童相談所の現状」.(参照2023-12-08).
児童福祉司の将来性
児童福祉司は今後さらに重要となる仕事です。
現代の日本では少子化問題が深刻ですが、児童相談所の相談対応件数は年々増加しています。2004年の相談件数は約35万件ですが、2015年の相談件数は43万件を超えています。現状はさらに増えていると推測されます。
この背景には、共働き、離婚、所得格差の拡大(貧困)、核家族化の増加などがあります。家庭が混沌としている状況では、子どもは問題行動を起こしやすくなる傾向にあり、児童福祉司の支援が必要となります。
その中で最も深刻な問題は、虐待です。児童相談所における虐待相談は、2014年から2019年までの5年間で10万件も増加しており、多くの子どもの人権や命が危険にさらされていることがわかります。
上記の背景を踏まえ、2016年に施行された「児童相談所強化プラン」には、児童福祉司の増員が盛り込まれました。2016年に3030人だった児童福祉司は2022年までに5783人まで増加するほど、国も力を入れて取り組んでいます。
さらに2023年には「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を決定し、2024年度までに児童福祉司を1,060人増員することなどを目標に掲げています。
このような社会状況を踏まえれば、今後ますます児童福祉司の役割の重要性が高まっていくことは明白です。
※相談件数について.「児童相談所の現状」.(参照2023-12-08).
※児童福祉司の増員について.「令和4年度における児童福祉司・児童心理司の配置状況について」.(参照2023-12-08).
児童福祉司になるにあたっての注意点
これまでの説明で児童福祉司の仕事内容や重要性がお分かりいただけたでしょうか?
さいごに、児童福祉司になるにあたっての注意点をご説明します。それは児童福祉司自身の「健康維持」についてです。
児童福祉司は、虐待を受け身体と心に傷を負った子どもたちと関わる機会が少なくありません。人間なら誰しもがショックを受けるシビアな状況も目の当たりにします。つまり心理的な負担感やプレッシャーを感じやすい職務内容と言えるでしょう。
また子どもだけでなく保護者の支援も行う児童福祉司は、保護者の気持ちと子どもの気持ちの間で板挟みになることもあります。そのようなときには対応が難しく感じられると思います。
子どもの明るい未来のためには、支援者である児童福祉司が必要です。しかしながら、まずは児童福祉司自身の心と身体が健康でなければ務まりません。
一人で解決しようと問題を抱えることは最も危険です。先輩・同僚と相談しあったり、ストレス発散方法や気持ちを切り替える術を身につけ、自身の健康に配慮しながら仕事をしましょう。
条件を満たして児童福祉司になろう
児童福祉司になるために特定の資格を取得する必要はありませんが、定められている条件のうちいずれかを満たす必要があります。指定の専門学校や講習会などの卒業・修了でも児童福祉司に慣れるため、高校生は該当の専門学校への進学も視野に入れるとよいでしょう。
心理学・教育学・社会学を専修する学科のある大学・大学院への入学も一つの方法です。今回ご紹介したように選択肢はいくつかあるので、自分に適した方法で児童福祉司を目指してください。
最近の投稿
カテゴリー
月別アーカイブ
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (2)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (4)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (3)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (6)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2019年2月 (1)
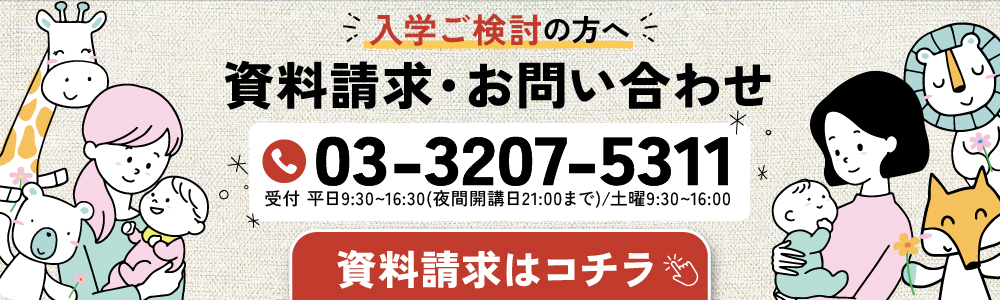
日本児童教育専門学校Japan Juvenile Education College